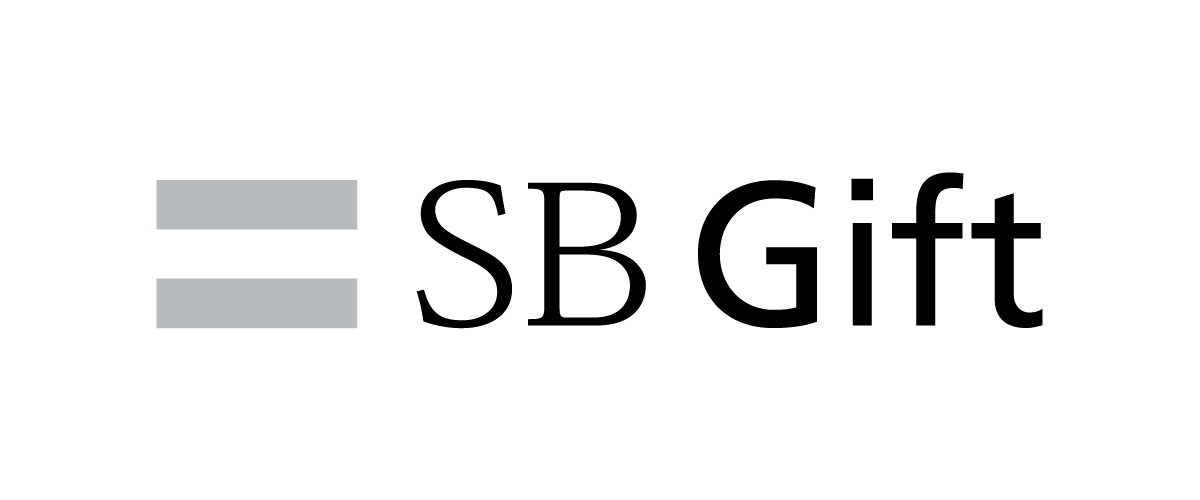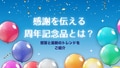顧客にアプローチするチャネルの選び方と特徴
企業と顧客をつなぐ重要な接点である「顧客チャネル」は、売上向上と顧客満足度向上の鍵を握る要素です。デジタル化の進展により、オンラインとオフラインを融合した新しいチャネル戦略が求められています。本記事では、各チャネルの特徴から成功事例まで、効果的な顧客アプローチの手法を解説します。
目次[非表示]
- 1.顧客チャネルとは?
- 2.顧客チャネルの種類と特徴
- 2.1.販売チャネル
- 2.2.コミュニケーションチャネル
- 2.3.オムニチャネル
- 2.4.クロスチャネル
- 2.5.マルチチャネル
- 3.顧客チャネル戦略の設計方法
- 4.成功事例に学ぶ効果的な顧客チャネル活用
顧客チャネルとは?
顧客チャネルとは、企業が顧客に製品やサービスを届けたり、顧客とコミュニケーションを取ったりするための経路や手段のことです。これは単なる販売ルートに留まらず、企業と顧客が接触するあらゆる場面を包含する概念として理解されています。
チャネルとは、マーケティング用語で集客を行うための媒体(流入経路)を指す言葉です。多くの顧客を集め、売上をあげるために、小売店やECサイト、インターネット広告やSNSなどがチャネルとして活用されています。
現代のビジネス環境では、顧客の購買行動が多様化し、デジタルとリアルを自由に行き来するようになっています。そのため、企業は複数のチャネルを効果的に組み合わせ、顧客との最適な接点を構築することが競争優位の源泉となっています。
顧客チャネルの種類と特徴
顧客チャネルは目的と機能によっていくつかの種類に分類されます。それぞれの特徴を理解し、適切に活用することで効果的な顧客アプローチが可能になります。

流通チャネル
流通チャネルは、顧客に製品やサービスを見せたり届けたりする経路のことを指すもので、商品が販売する側のもとから、購入する側に届くまでの流通ルートにおけるあらゆる手段を含みます。具体的には、流通業者、卸売業者、小売業者が流通チャネルに該当します。
流通チャネルには段階があり、0段階から3段階までの4つの段階があり、段階が増えれば増えるほど中間マージンがかかるため、生産者の利益が少なくなります。0段階チャネルは企業が直接販売する直販モデル、1段階チャネルは小売業者を経由、2段階チャネルは卸売業者と小売業者を経由する形態です。
近年では、SNSやフリーマーケットアプリなどの台頭により、生産者と消費者の直接取引が増えている傾向があります。これにより、中間マージンを削減し、顧客により良い価格で商品を提供することが可能になっています。
販売チャネル
販売チャネルは、顧客へ製品やサービスの販売を行なうチャネルのことで、小売業者のほか、Eコマースなどが相当するものです。実際に消費者が商品やサービスを購入できる販売する場所であり、顧客との最終的な取引が行われる重要な接点となります。
現代の販売チャネルは多様化が進んでおり、最近ではInstagramなどでもEコマース機能が追加されたことで、ECサイトよりも、Instagram経由で買い物をする若者が増えているという変化も見られます。
主な販売チャネルには、実店舗、ECサイト、ショッピングモール、SNS販売、テレビショッピング、カタログ通販などがあります。それぞれのチャネルには特徴があり、ターゲット顧客層や商品特性に応じて最適な選択が求められます。
コミュニケーションチャネル
コミュニケーション・チャネルは、顧客にメッセージを送ったり、顧客からメッセージを受け取るためのチャネルを指し、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、手紙、電話、屋外広告、チラシ、インターネットなどが相当するものです。
企業が顧客とコミュニケーションをとるための場所や方法として機能し、メールやSNS、アプリ、ダイレクトメール、テレビCM、webサイト、web広告、電話など多岐に渡ります。
特に近年では、コミュニケーションチャネルは、企業から消費者へメッセージを送るだけでなく、消費者からのメッセージを受け取る役割も果たしています。双方向のコミュニケーションが可能になったことで、顧客のフィードバックを即座に収集し、商品・サービスの改善に活かすことができるようになっています。
オムニチャネル
オムニチャネルは、すべてのチャネルが完全に統合され、顧客がどのチャネルを利用しても同一のブランド体験を得られることを目指します。最大の違いは、マルチチャネルがそれぞれ独立したチャネル運営であるのに対し、オムニチャネルはすべてのチャネルをデータ連携・システム統合することにあります。
オムニチャネル化を実現できれば顧客にとっての利便性が高まるため、顧客体験 (CX)向上が期待できます。顧客満足度も相関的に上がりやすくなり、自社の商品やサービスに対するイメージもよくなる可能性が高いです。
実際の効果として、顧客が自分のペースで複数のチャネルを使い分けながら購買プロセスを進められる環境が整うことで、購買に至るまでのストレスが大幅に軽減されます。また、チャネル間での情報の一貫性により、顧客体験の質が向上し、長期的な顧客関係の構築に寄与します。
クロスチャネル
クロスチャネルとは、複数のチャネルを連携させて顧客にサービスを提供する手法です。オムニチャネルとは異なり、チャネル間でのデータ完全統合ではなく、特定の機能やサービスでチャネルを横断して活用する戦略です。
例えば、オンラインで注文した商品を実店舗で受け取るサービスや、店舗で商品を確認してからオンラインで購入するといった、チャネル間の連携によって顧客利便性を向上させる取り組みが該当します。
クロスチャネル戦略の特徴は、各チャネルの強みを活かしながら、顧客の購買行動に合わせて柔軟にサービスを提供できる点にあります。完全なシステム統合を必要としないため、比較的導入しやすい一方で、チャネル間の連携を適切に管理することが成功の鍵となります。
マルチチャネル
マルチチャネルは複数の販売チャネルを並行して運営する戦略である一方、オムニチャネルはすべてのチャネルが完全に統合され、顧客がどのチャネルを利用しても同一のブランド体験を得られることを目指します。
マルチチャネルの特徴は、各チャネルがそれぞれ独立して運営される点にあります。実店舗、ECサイト、電話注文、カタログ販売など、複数の販売経路を同時に展開することで、より多くの顧客層にアプローチできます。
しかし、従来のマルチチャネルではチャネルごとに分散していた顧客データが、オムニチャネルでは統合的に管理されることで、顧客の購買行動の全体像を把握することが可能になるという課題があります。そのため、現在では単純なマルチチャネルから、より統合されたオムニチャネル戦略への移行が進んでいます。
顧客チャネル戦略の設計方法
効果的な顧客チャネル戦略を構築するためには、体系的なアプローチが必要です。ターゲット顧客の理解から始まり、適切なチャネルの選択と組み合わせを検討することが重要です。

ターゲット顧客の特定と分析
ターゲット分析および競合調査をしっかりと行うことです。例えば、スターバックスが行ったようにターゲットとなる顧客層を明確にし、そのニーズに応じた施策を打つことが重要です。ターゲット顧客の特定と分析は、チャネル戦略成功の基盤となる重要なプロセスです。
まず、既存顧客のデータ分析を通じて、顧客の属性、購買行動、利用チャネルの傾向を把握します。年齢、性別、地域、職業などの基本属性に加え、購買頻度、購買金額、季節性などの行動パターンを詳細に分析することで、顧客セグメントを明確化できます。
次に、各セグメントの顧客がどのチャネルを好んで利用するかを調査します。ターゲット層にアプローチしやすい販売チャネルを選択することが成功のカギとなる。販売チャネルは多いほど消費者の目に触れやすいが、運営コストもかかるため、ターゲット層が使いにくいチャネルをやみくもに増やしても利益は出づらいためです。
また、顧客の購買プロセスを詳細にマッピングし、認知から購買、アフターサービスまでの各段階で、どのチャネルが最も効果的かを検討します。この分析により、顧客体験を最適化するためのチャネル戦略を設計できます。
成功事例に学ぶ効果的な顧客チャネル活用
実際の企業事例を通じて、効果的な顧客チャネル戦略の実践方法と成功要因を学びます。各企業がどのような課題を解決し、どのような成果を上げているかを具体的に見ていきます。
大手企業の顧客チャネル戦略事例
ユニクロのアプリは、2021年には国内で5700万人、グローバルでは1.4億人の会員を抱えるまでに成長しました。また、店舗受取を利用することによって送料を無料にするなど、顧客にとってもメリットが大きく、実店舗への来店も促進されています。
ユニクロの成功要因は、AIを活用したパーソナライゼーションとチャネル間の利便性向上にあります。専用アプリにお買い物アシスタントの「IQ」を導入し、ユーザーはいつでもどこでも、商品選びやサイズ選びを手伝ってもらうことができます。さらに、アプリ限定価格やクーポンの提供により、デジタルチャネルと実店舗の相乗効果を最大化しています。
セブンイレブンは、「Omni7」というサービスを実施しました。これは、セブンイレブンが運営しているECサイト(オムニ7)で注文した商品を、イトーヨーカドーやそごうなどの自宅近くの店舗で受け取ることができるサービスです。この取り組みにより、2016年2月期決算の発表によると、ECサイトの売上は1400億を超えました。
また、スターバックスは、顧客体験を向上させるためにアプリと店舗の連携を強化しました。これにより、デジタルツールと物理店舗を統合し、顧客が店舗での購入プロセスを円滑に進められる仕組みを提供しています。モバイルオーダーとピックアップサービスの組み合わせにより、待ち時間の短縮と利便性の向上を実現しています。
顧客満足度向上につながるチャネル戦略
オムニチャネル化すると、各チャネルで商品の購入を検討している顧客のデータを統合的に管理できるようになります。それぞれに最適なアプローチをかけられるため、顧客との関係性を継続的に深化させることが可能になります。
顧客満足度向上の鍵となるのは、チャネル間の一貫性です。チャネル間での情報の一貫性により、顧客は何度も同じ情報を入力する必要がなくなり、よりスムーズで快適な購買体験を享受できるようになります。
また、顧客が複数のチャネルで一貫した体験を重ねることで、ブランドに対する信頼感と愛着が醸成されます。また、顧客の購買履歴や行動データを統合して管理することで、個々の顧客に最適化されたサービスや商品提案が可能となり、リピート購入の促進につながります。
データ統合による効果として、MAツールの活用により、収集したデータを効果的に分析し、顧客セグメンテーションの精度向上や、適切なタイミングでのアプローチが実現できます。これにより、顧客一人ひとりに最適化されたコミュニケーションが可能になり、満足度の向上につながります。
デジタルギフトを活用した成功事例
らあめん花月嵐を展開するグロービート・ジャパン株式会社では、従来の紙クーポンから『ポチッとギフト』へと移行することで、顧客チャネル戦略の大幅な改善を実現しました。同社では長年、チラシの折込やラーメン専門誌への紙クーポン掲載を続けてきましたが、回収率が低く、費用や手間に対して効果が見合わないという課題を抱えていました。
デジタル化の決め手となったのは、プラットフォームが固定されておらず新規顧客にも幅広くリーチできる点と、コピペ利用といった不正リスクに対する対策が講じられていたことでした。導入により、店舗・本部ともに作業時間を大幅に削減でき、結果もすぐに数字で見えるようになったという効果を得ています。
特に注目すべきは、アンケート施策との連携です。従来は紙のアンケートの回収率が高く、デジタル化に踏み切れずにいましたが、『Webキャンペーンシステム』を活用してアンケート回答者にその場でデジタルクーポンを発行する仕組みを構築した結果、アンケートの回収率は3割アップしました。
この事例は、デジタルギフトが単なる特典配布ツールを超えて、オンラインとオフラインを自然につなぐ効果的な顧客チャネル戦略の一環として機能することを示しています。リアルタイムでの利用状況把握や効果測定も可能なため、PDCAサイクルを回しながら継続的な改善を図ることができる点も大きなメリットとなっています。
らあめん花月嵐を展開するグロービート・ジャパン様の事例はこちら