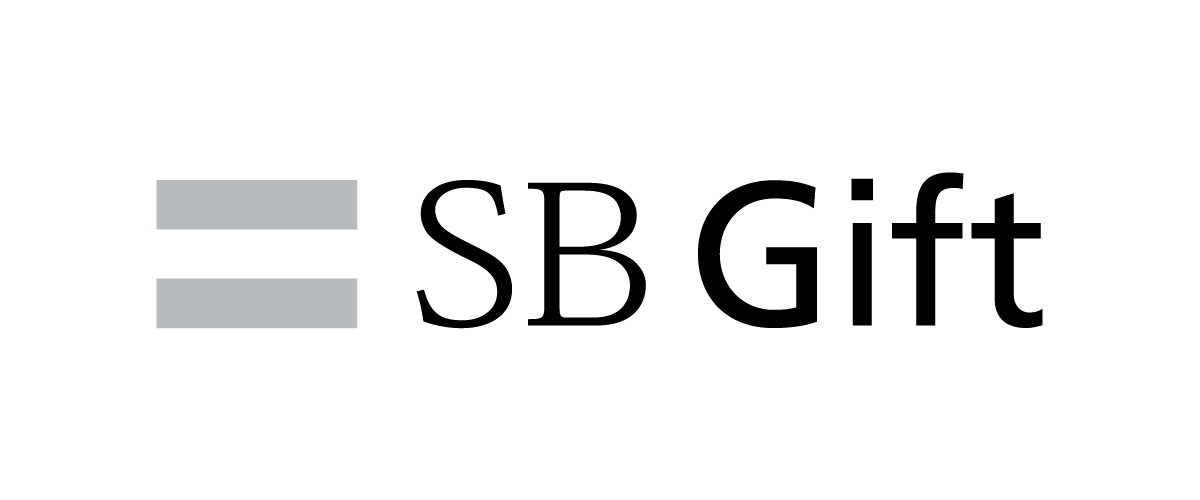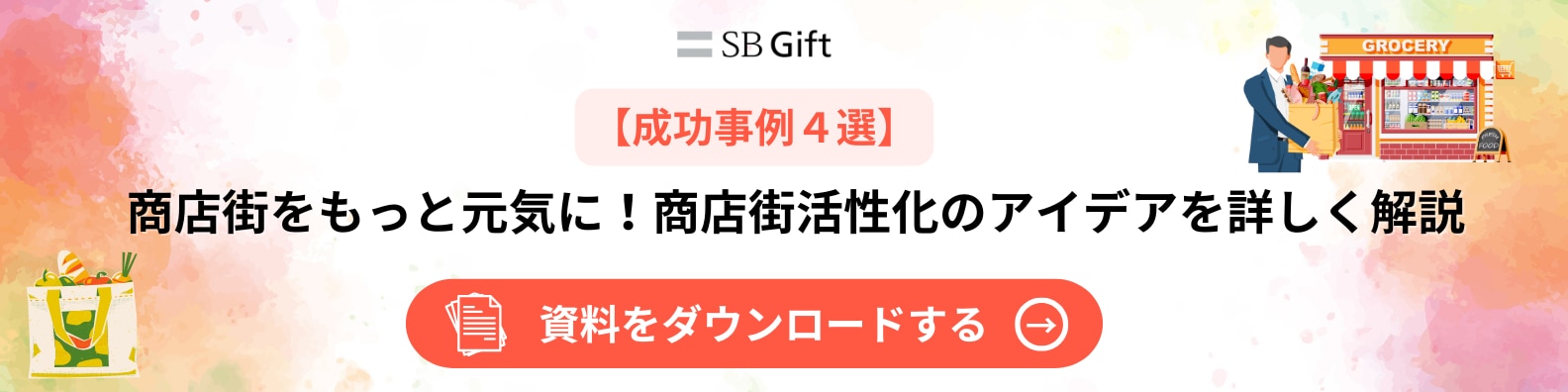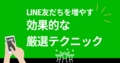【成功事例4選】商店街をもっと元気に!商店街活性化のアイデアを詳しく解説
全国各地で商店街の衰退が課題となっている中、効果的な活性化策を求める声が高まっています。しかし、成功事例に学び、適切な支援策を活用することで、商店街は地域の賑わいを取り戻すことができます。本記事では、商店街活性化のための具体的なアイデアと、実際に成功を収めた4つの事例を詳しく解説します。また、活用できる国の支援策から、最新のデジタル施策まで、商店街の未来を明るくする方策をご紹介していきます。
目次[非表示]
- 1.商店街が衰退してしまう理由
- 1.1.日本における商店街の現状
- 1.2.商店街が抱える課題
- 1.2.1.経営者および顧客の高齢化と後継者不足
- 1.2.2.空き店舗の増加とその影響
- 1.2.3.行政の支援不足とまちづくり計画の欠如
- 1.2.4.商業施設の郊外進出と来街者の減少
- 2.成功事例4選から学ぶ商店街活性化のヒント
- 3.商店街活性化を支援する国の施策を紹介
- 3.1.補助金や助成金の概要
- 3.1.1.補助金の種類と申請の流れ
- 3.2.自治体との連携による支援
- 3.2.1.都道府県と市町村の連携
- 3.2.2.官民連携の取り組み
- 3.3.活用事例の紹介
- 3.3.1.福井県福井市の「美のまちプロジェクト」
- 3.3.2.宮崎県日南市の「油津アーケード農園」
- 3.3.3.新潟県新潟市の長屋改修プロジェクト
- 4.商店街の認知拡大・誘致にはデジタルクーポンが最適
商店街が衰退してしまう理由
商店街の衰退は、様々な社会的要因が複雑に絡み合って起きています。ここでは、現状の分析と、商店街が直面している具体的な課題について見ていきましょう。
日本における商店街の現状
日本の商店街は、かつて地域コミュニティの中心として栄えてきましたが、近年ではその多くが停滞または衰退の一途をたどっています。内閣府の「商店街調査」によると、直近の調査で「繁栄している」と回答した商店街はわずか2.3%に過ぎず、9割以上が「停滞」もしくは「衰退」している状況です。これは商店街全体の活力が著しく低下していることを示しています。
出典:第2部 第1章 1.現状の確認 - 内閣府
また、香川大学経済学部の黒川氏の研究では、商店街を構成する小規模商店(従業員4名以下)の数が1998年の130万店から2007年には76万店へと減少しています。この大幅な減少は、商店街の経営基盤が弱体化しており、持続可能性に対する懸念が高まっていることを裏付けています。
出典:新しい時代の商店街の再生に向けて
さらに、中小企業庁の「小規模企業白書」(2020年版)では、商店街が地域の生活インフラ機能を支えながらも、多数の課題に直面している現状が詳述されています。この白書によると、商店街は地域住民の消費活動において重要な役割を果たしているものの、その活性化には多方面からの支援と取り組みが必要とされています。
商店街が抱える課題

経営者および顧客の高齢化と後継者不足
商店街が直面する最も深刻な課題の一つが、経営者および常連顧客の高齢化と後継者不足です。多くの商店街運営者が高齢化しており、後を継ぐ若手が不足しているため、商店街の多くの店舗が閉店に追い込まれています。これにより、空き店舗が増加し、商店街全体の魅力が低下するという悪循環が生まれています。
空き店舗の増加とその影響
商店街内の店舗数の減少は、空き店舗問題として顕在化しています。埼玉県が実施した調査によれば、商店街の7割以上に空き店舗が存在し、その多くが将来的にも増加する見込みです。空き店舗の増加は商店街の景観を損なうだけでなく、来街者の減少を招き、さらに商店街の衰退を加速させる要因となっています。また、空き店舗が放置されることで、地域全体の治安や安全性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
出典:第1節 商店街が抱える課題 - 埼玉県
行政の支援不足とまちづくり計画の欠如
空き店舗対策には行政からの支援が不可欠ですが、多くの商店街では十分な支援を受けられていない現状があります。商店街連合会の調査では、空き店舗対策に「特に関与していない」と回答する商店街が57.6%を占めており、まちづくり計画の立案情報の提供や支援策の実施が不足していることが明らかになっています。このため、商店街自身が主体的に空き店舗問題に取り組むことが困難になっており、持続的な活性化が阻害されています。
出典:事例から学ぶ!「商店街を、もっと元気に」 - ミラサポPlus
商業施設の郊外進出と来街者の減少
ライフスタイルの変化や郊外型の大型商業施設の出店により、従来の商店街への来街者が減少しています。これにより、商店街の収益性が低下し、新規店舗の開設や既存店舗の維持が困難になっています。消費者がより便利で多様な選択肢を求めて商店街から離れる傾向が強まっており、商店街の活性化をさらに難しくしています。
成功事例4選から学ぶ商店街活性化のヒント
全国には、様々な工夫で活気を取り戻した商店街が存在します。これらの成功事例から、具体的なヒントと実践的な戦略を学んでいきましょう。
事例その1
北海道札幌市の麻生商店街は、空き店舗を有効活用し、地域の子どもたちへの学習支援と食事提供を行う「子ども食堂」を開設しました。平成25年に「へるすたでぃ・藤麻人(とまんと)」としてスタートし、平成26年には「麻生キッチンりあん」に名称を変更、さらに平成28年にはより広い空き店舗へ移転して「子ども食堂」を開始しました。
この取り組みでは、ひとり親家庭の子どもを対象に栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、学習支援を行っています。運営には藤女子大学の学生が参加し、栄養面は大学の栄養学科の教授とゼミ生、調理面は地域のボランティア、学習支援はNPO法人Kacotamが担当しています。また、資金調達のためにオリジナルグッズや北海道各地の特産品を販売するイベントも定期的に開催されています。
このプロジェクトは、空き店舗の有効利用だけでなく、地域コミュニティの再生にも寄与しており、商店街全体の魅力向上につながっています(商店街活性化で地域の魅力を発信!)。
事例その2
福岡県大牟田市の銀座通り商店街では、「街なかストリートデザイン事業」を中心に空き店舗のリノベーションを進めています。このプロジェクトでは、プロの業者だけでなくアマチュアも参加する「DIYリノベーション」イベントを実施し、地域住民や若手クリエイターの参加を促進しました。
具体的な取り組みとして、海外経験を持つシェフによるイタリア料理店の新規出店や、廃線となった路面電車を活用したカフェ「hara harmony coffee」の開業、定期的なマルシェやワークショップの開催などがあります。これらの活動は新聞取材やSNSを通じて広く宣伝され、クラウドファンディングによる資金調達も行われました。その結果、商店街のファンや新規出店希望者が増加し、商店街全体の活性化に成功しています。
事例その3
群馬県前橋市の前橋中央通り商店街では、空き店舗を活用して学生用シェアハウス「シェアフラット馬場川」を整備しました。このプロジェクトは、前橋工科大学と地元商店主による協働で始動し、若者離れが進む商店街に学生を呼び込むことで日常的な賑わいを創出しています。
学生たちが商店街の生活者として定期的に参加することで、商店街や自治会活動への積極的な関与が促進されています。さらに、学生たちがシェアハウスでの生活を通じて商店街の魅力を発見し、その体験を通じて商店街の発展に貢献する姿勢が強化されています。この取り組みは、若者の定住促進と商店街全体の活性化に寄与しています。
事例その4
東京都目黒区の都立大学商店街では、「とりつじん実行委員会」を設立し、次世代へのスムーズなバトンタッチを目的としています。30~40代の若手メンバーを中心に、「あえて商店街らしくない商店街事業」を推進し、予算と権限を与えることで商店街の人材の新陳代謝を図っています。
具体的な活動として、商店街の魅力を紹介するガイドブック「とりつじん」の作成、ミニ講座「とりつ大学」の開催、店舗間の協力を促進する回遊イベント「とりつイベント」の実施などがあります。これらの取り組みにより、若手世代への商店街の継承が進み、商店街全体の知名度も向上しました。また、メディアに取り上げられることでさらなる集客効果が期待されています。
商店街活性化を支援する国の施策を紹介

商店街の活性化に向けて、国や自治体は様々な支援策を用意しています。ここでは、活用できる制度や支援策について、具体的な事例とともに解説します。
補助金や助成金の概要
補助金と助成金はいずれも事業者に対する経済的支援ですが、性質や支給条件に違いがあります。例えば、補助金は特定の事業や活動に対して支給されるもので、公募期間が短く、通常1ヶ月程度と限定的な場合が多いです。一方、助成金は継続的な支援を目的としており、通年で募集されることが多いです。また、助成金は主に厚生労働省が管轄し、雇用や労働環境の改善などに重点を置いている傾向があります。
補助金の種類と申請の流れ
補助金には、事業の内容や規模に応じて様々な種類があります。代表的なものとしては、小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、IT導入補助金などが挙げられます。これらの補助金は、事業計画の作成から申請、採択、交付、事業実施、実績報告、請求、支払いといった一連の流れを経て支給されます。
- 公募開始:補助金の募集が開始され、応募期間が設定されます。
- 申請書作成:事業計画書など必要書類を準備します。
- 補助金申請:所定の方法で申請を行います。
- 採択:審査を経て、支給が決定された事業者が選ばれます。
- 交付申請:補助金の受領手続きを行います。
- 事業実施:補助金を活用して事業を実施します。
- 実績報告:事業の成果を報告書として提出します。
- 請求:支出した費用の請求を行います。
- 支払い:補助金が交付されます。
補助率は事業内容や規模によって異なり、一般的には補助金の2/3が支給されることが多いです。ただし、赤字事業者の場合は補助率が3/4に引き上げられる場合もあります。
自治体との連携による支援
商店街活性化を成功させるためには、国の補助金や助成金だけでなく、地方自治体との連携も欠かせません。自治体は地域特性に合わせた支援策を展開しており、商店街の持続的な発展を支える重要な役割を果たしています。
都道府県と市町村の連携
近年、地方分権改革の進展により、都道府県が市町村に対する支援や補完を強化しています。例えば、都道府県は市町村と協力して専門人材の育成や共通のプロジェクトの推進を行うことで、商店街に対する総合的な支援を提供しています。しかし、実際には小規模な市町村ではこの連携が十分に機能していないケースも見受けられ、さらなる協力体制の構築が求められています。
官民連携の取り組み
自治体と民間企業、NPO法人との連携も、商店街活性化において有効な手段です。例えば、福岡県大牟田市の銀座通り商店街では、空き店舗のリノベーションを民間のDIYイベントと連携して行い、商店街全体の魅力を高める取り組みが成功しています。また、自治体と民間団体が協力してヤングケアラー支援を行うケースも増えており、これにより地域住民の生活環境が向上するとともに、商店街への来訪者も増加しています。
活用事例の紹介
商店街の空き店舗を活用した取り組み
商店街の空き店舗を活用した官民連携の取り組みは、地域活性化において重要な役割を果たしています。補助金や助成金を活用した具体的な事例をご紹介します。
福井県福井市の「美のまちプロジェクト」
福井市では、駅前の空き店舗増加に対処するため、5つの商店街が連携して「福井駅前五商店街連合活性化協議会」を設立しました。この協議会は、「美しくなれるまち」をテーマに掲げ、平成27年に美容関連の店舗11店を一斉にオープンさせました。この取り組みでは、空き店舗の活用や新規開業の支援、出店促進、地元ショッピングモールとの連携など、官民が協働して地域の基盤整備と魅力向上を図りました。
宮崎県日南市の「油津アーケード農園」
日南市では、「4年で20店舗誘致」という目標を掲げ、商店街再生プロジェクトを推進しました。その初期段階で企画されたのが「油津アーケード農園」です。商店街のアーケード内にある約100㎡の空き地を活用し、「商店街アーケードで農業!?」という斬新なコンセプトで、市民がまちと関わりを持つ機会を創出しました。この取り組みは、若い世代へのアプローチとしても効果的であり、まちの雰囲気を一新することに成功しました。
新潟県新潟市の長屋改修プロジェクト
新潟市では、閉店が相次ぎシャッター通りと化した長屋を、民間主体で改修し、テナントミックスの形で空き店舗を解消しました。この取り組みにより、商店街全体の魅力が向上し、人々の往来が増加しました。
これらの事例は、官民が連携し、補助金や助成金を効果的に活用することで、商店街の空き店舗を再生し、地域の活性化につなげた成功例です。各自治体や地域の特性に合わせた柔軟な取り組みが、持続可能なまちづくりに寄与しています。
商店街の認知拡大・誘致にはデジタルクーポンが最適
デジタル技術を活用した集客施策は、現代の商店街に欠かせない要素となっています。特にデジタルクーポンは、効果的な集客ツールとして注目を集めています。
SBギフトは、自治体向けに特化したデジタルクーポンサービス「地域活性化クーポン」を提供しています。このサービスは、自治体が地域特有のニーズに応じたクーポンを簡単に作成・管理・配布できる機能を備えており、以下のようなメリットがあります。
- 認証機能による特典の豪華化と利用率向上:顧客がクーポンを利用する際に認証機能を導入することで、特典の信頼性が高まり、利用率が向上します。
- 配布・集計の効率化でコスト削減:デジタルクーポンは配布や集計が自動化されるため、人的コストや時間を大幅に削減できます。
- リアルタイムの利用状況確認による効果的なマーケティング:クーポンの利用状況をリアルタイムで把握することで、即時にマーケティング戦略を調整することが可能です。
これらの機能により、自治体は効率的かつ効果的にクーポンを活用し、地域全体の活性化を図ることができます。また、SBギフトの地域活性化クーポンは多言語対応や柔軟なカスタマイズが可能なため、多様な地域ニーズに応えることができます。
SBギフトの地域活性化クーポンは、東京都浴場組合などの自治体で既に成功事例を生み出しています。これらの事例では、デジタルクーポンを活用することで、地域特産品や観光施設の利用促進、地域経済の活性化を実現しています。具体的には、電子クーポンを通じて消費者の行動を把握し、効果的なプロモーションを展開することで、地域全体の売上向上に寄与しています。