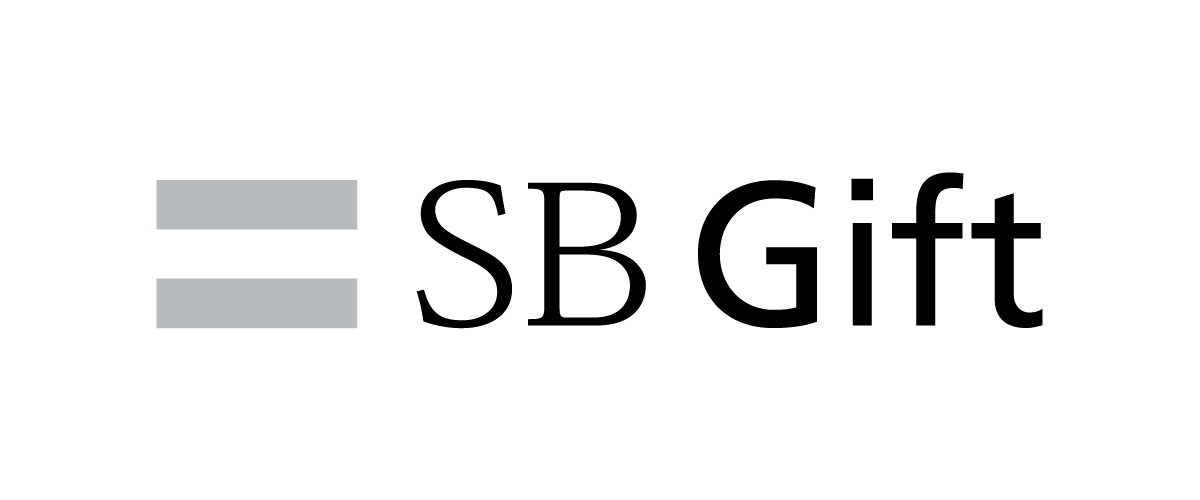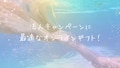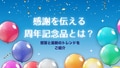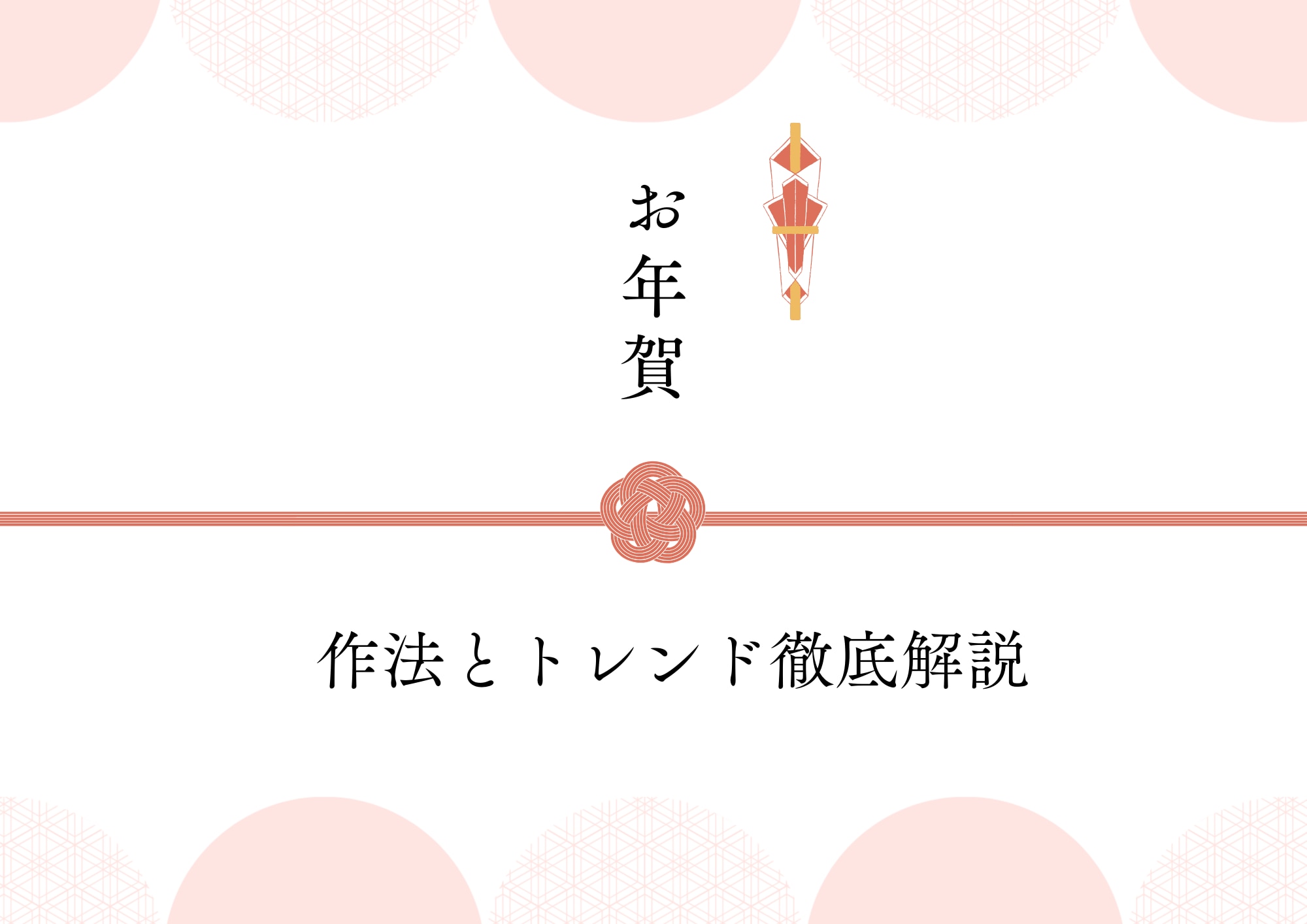
お年賀とは何か?作法とトレンド徹底解説
新年を迎えると多くの方が「お年賀」という言葉を耳にしますが、正しい意味や作法についてご存知でしょうか。企業の営業活動においても重要な役割を果たすお年賀について、基本的な知識から最新のトレンドまで幅広く解説いたします。
目次[非表示]
- 1.お年賀の基本とは
- 1.1.お年賀の歴史と由来
- 1.2.お年賀を贈る時期
- 1.3.お年賀とお歳暮の違い
- 1.4.お年賀の贈り方の基本
- 2.お年賀の贈り物の選び方
- 2.1.お年賀のトレンド
- 2.2.NGなお年賀アイテムとは
- 3.企業におけるお年賀の活用
- 3.1.取引先との関係強化におけるお年賀
- 3.2.デジタル時代のお年賀のあり方
お年賀の基本とは
お年賀の正しい理解と実践のために、まずは基本的な知識を身につけることが重要です。歴史や由来から現代における贈り方まで、体系的にご紹介いたします。
お年賀の歴史と由来
お年賀は、日本の古くからの文化である新しい年の神様をお迎えして祀る習慣が由来といわれています。古来、お正月の挨拶をする際には、神様を祀る神棚やお仏壇へのお供え物として「御歳魂(おとしだま)」を持参していました。この習慣が現代に受け継がれ、現在では、そのお供え物が新年の挨拶回りに持参するお年賀になったと考えられています。
お年賀は、実家の両親や親戚、職場の上司、取引先など、目下の人から目上の人へ贈るのが一般的です。新年に「今年もよろしくお願いします」という気持ちを込めて手土産として持参する習慣として定着しており、日本の伝統文化として大切にされています。
お年賀を贈る時期
お年賀は、一般的に1月2日から松の内までに渡すのがマナーで、関東では7日、関西では15日頃までが目安とされています。お年賀を贈る適切な時期は、一般的に1月2日から松の内(正月の松飾りのある期間)までとされています。松の内の期間は地域によって異なりますが、関東地方では1月7日まで、関西地方や名古屋などでは1月15日までとされています。
また、お年賀を元旦に贈るのは避けてください。仕事の年始回りでお年賀を贈る場合は、1月15日頃までに済ませるのがよいでしょう。時期を過ぎてしまった場合は、松の内に間に合わない場合は、立春までの間に「寒中見舞い」としてお贈りします。
お年賀とお歳暮の違い
お年賀は「新年もよろしくお願いします」とお付き合いをお願いする気持ちが込められた贈り物です。一方で、お歳暮は、お世話になった方への年末のご挨拶で、今までに対する感謝の気持ちを込めて贈るものです。
「お年賀」の起源は、新しい年神様をお迎えして祀ることにあります。現在「お年賀」とは、「今年もどうぞよろしくお願い致します」という、「これからに対する挨拶」の気持ちを込めて年始回りの際に挨拶の品物として持参するものを指します。贈る時期についても、お歳暮は11月末頃から12月31日頃まで、お年賀は1月2日から松の内までと明確に分かれています。
お年賀の贈り方の基本
お年賀は本来持参する贈り物であり、新年の挨拶をする際に手土産として直接手渡しするのが基本です。訪問する際は、事前に連絡して相手の都合のよい日程を確認しておきましょう。お年賀を渡す際は、相手の都合に配慮し、事前に訪問可能な日時を確認することが大切です。元旦や午前中は避け、午後の時間帯、特に午後13~14時ごろの訪問が適しています。
お年賀の贈り物には、紅白の蝶結びの水引が付いたのし紙を掛けます。表書きには「御年賀」または「お年賀」と記し、水引の結び目の下に贈り主の名字を記入しましょう。また、予算相場は3,000円程度ですが、安価すぎても高価すぎても失礼に当たるため、贈る相手や付き合いの程度によって金額を考慮するのが望ましいといえます。
お年賀の贈り物の選び方
適切なお年賀を選ぶには、最新のトレンドを把握し、避けるべきアイテムについても理解しておくことが大切です。相手に喜ばれる贈り物を選ぶためのポイントをご紹介します。

お年賀のトレンド
2026年のお年賀ギフトをお考えの方へ。今年もそろそろ終盤。新しい年がすぐそこまで近づいてきましたね。お世話になっている方へ、皆さんの健康と幸せ、そして家内安全を願って、お年賀ギフトをお贈りしましょう。
2026年のお年賀トレンドとして、2026年の『干支・午』の絵が描かれたデザインの冬季限定のギフトです。干支にちなんだアイテムが人気を集めています。また、日本で長い間人気の和菓子は、老若男女を問わず幅広い世代の人に喜ばれます。上品できちんとした印象の商品が多いのも、目上の人に渡すお年賀におすすめの理由です。
お年賀の相場は、3,000円前後が多いです。勤務先の上司やお取引先、親や親戚などは、3,000円まで、近所の方などには、2,000円までの品物を贈る方が多いようです。贈り物の選択肢としては、予算の相場は1,000円~3,000円程度、高くても5,000円程度までが主流です。アイテムは日持ちのよいスイーツや和菓子、お酒、タオルなどが人気です。
NGなお年賀アイテムとは
お年賀を選ぶ際には、避けるべきアイテムについても理解しておく必要があります。お祝いに贈ると良くないとされる代表的な品物は「櫛(くし)」「ハンカチ」「刃物」の3つです。いずれも語呂合わせや、使い方からの連想から縁起が悪いと考えられています。
ハサミや包丁、ナイフなどの刃物類は、「縁が切れる」ことを連想させてしまう品物です。また、目上の方に現金を差し上げるのはNGです。商品券はお金じゃないと思われるかもしれませんが、金額(額面)も書いてありますし、お金とほとんど変わりません。
その他にも、火事を連想させてしまうという謂われがあります。他にもライターや灰皿、ランプなど今ではオシャレな雑貨として取り扱われている品物にもNG商品が潜んでいますよ。ちなみに火を連想させる赤色の物もあまり好まれません。これらのアイテムは、縁起を重んじる新年の贈り物としては適さないため、避けることが大切です。
企業におけるお年賀の活用
ビジネスシーンにおいてお年賀は、取引先との関係強化や新時代の営業戦略として重要な役割を担っています。効果的な活用方法をご紹介します。

取引先との関係強化におけるお年賀
ビジネスではお年賀が重要だといわれますが、それはなぜなのでしょうか。お年賀の始まりとなった「年始回り」の風習を理解すると重要だとされる意味がわかるため、まずは確認してみてください。お年賀は、新年のご挨拶として贈るギフト。相手への敬意や、感謝の気持ちを伝える大切な機会でもあります。ビジネスシーンでは、相手との信頼関係を深め今後より良い関係を築くきっかけにもなります。
取引先(発注先)からのお年賀では『1,000円程度』『3,000円程度』『5,000円程度』が横一線に。『5,000円以上』のお年賀も『取引先(お客さま)』の場合の約2倍に増えています。これは取引先との関係性の重要度を反映していると考えられます。
個人向けのお年賀で『食品』『和菓子』『洋菓子』が上位を占めるのに対し『タオルなどの日用品』が企業向けのお年賀の断トツ1位です。企業向けでは実用性を重視した贈り物が好まれる傾向にあります。
デジタル時代のお年賀のあり方
現代のビジネス環境において、近年、年賀状をメールで送るという選択肢は企業やビジネスシーンにおいて急速に広まっています。デジタル化の波は、お年賀の形にも変化をもたらしています。
デジタルギフトとは、オンライン上でギフトコードを贈り、そのギフトコードを受け取った方が商品に引き換えたり金券として利用したりすることができるサービスです。発行されたギフトURLをメールやSNSで送付するだけで簡単にギフトを贈ることができるため、遠く離れた方への配送にかかる時間や費用を気にしなくてよかったり、急いでギフトを準備する必要がある際にも便利です。
デジタル時代のお年賀として、メールにデジタルギフトを添付して贈る方法が注目されています。この新しい形のお年賀は、在庫管理や発送コストを抑えて、簡単にギフトを贈れます。また、デジタルギフトのなかには、受け取ったユーザーが自分で好きなギフトを選べるサービスがあります。これにより、相手の好みを正確に把握していなくても、喜ばれる贈り物が可能になります。
SBギフトの「えらべるポチッとギフト」なら、メールで簡単にデジタルギフトを贈ることができ、受け取った方が好みの商品を選択できる現代的なお年賀の形を実現できます。
詳しくは
https://www.softbankgift.co.jp/select_pocchitto
をご覧ください。
従来の手渡しによるお年賀と併用することで、より効果的な新年のご挨拶が可能になるでしょう。