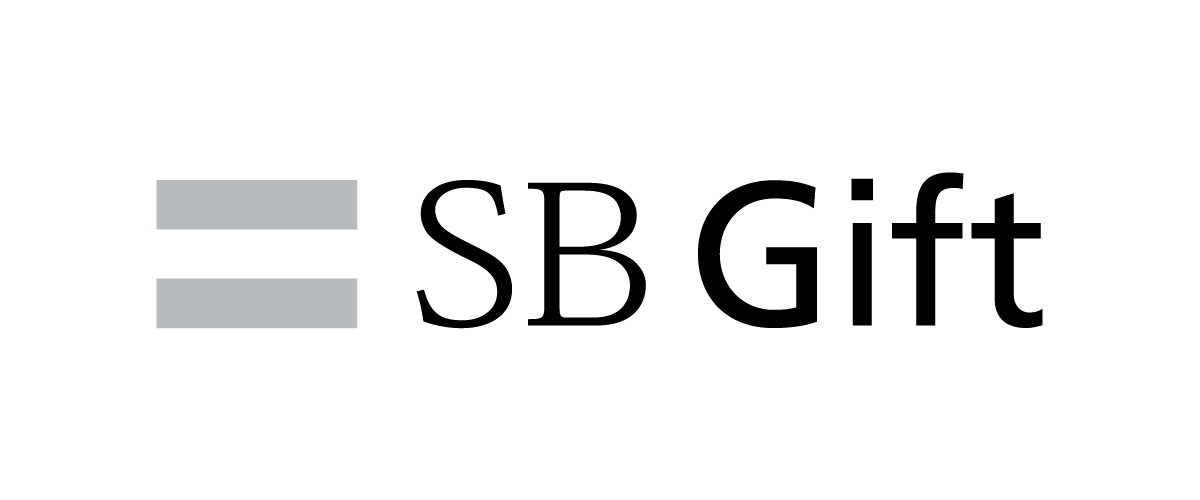観光が生む地域活性化の効果とその振興策
観光振興策は地域の活性化に大きな役割を果たし、多様な効果をもたらしています。経済的側面では収入増加や雇用創出を促し、社会的側面では地域文化の再評価や住民の誇りの醸成に貢献しています。本記事では、観光振興策が地域にもたらす様々な効果と、効果的な観光振興施策について詳しく解説します。地域の持続可能な発展に向けた観光の可能性について、具体的事例を交えながら探っていきましょう。
目次[非表示]
- 1.観光振興策が地域にもたらす経済的・社会的効果
- 1.1.地域経済への直接効果
- 1.2.雇用の創出と観光関連産業の成長
- 1.3.税収増加と自治体への影響
- 1.4.地域文化の再評価と保護
- 2.地域ブランドやデジタル化などの観光振興施策
- 2.1.地域特産品の開発と市場拡大
- 2.2.観光イベントの効果的な企画と実施
- 2.3.伝統工芸と観光の連携
- 2.4.観光マーケティングにおけるSNSの活用
- 2.5.デジタル技術を活用した観光案内
観光振興策が地域にもたらす経済的・社会的効果
観光振興策は単なる観光客数の増加だけでなく、地域に多面的な価値をもたらします。ここでは、観光振興が地域にもたらす経済的・社会的効果について、具体的な側面から掘り下げていきます。
地域経済への直接効果
観光振興は地域経済に多岐にわたる直接的な経済効果をもたらします。観光客が地域を訪れることで、宿泊、飲食、交通、買い物など様々な分野での消費活動が生まれ、地域経済を活性化させます。観光庁の発表によると、2019年の国内旅行消費額は2011年と比較して約2兆円増加しており、観光産業の経済効果の大きさを示しています。
観光による経済効果は直接消費だけでなく、波及効果も含めると非常に大きなものとなります。国土交通白書によれば、観光に係る直接消費は20.6兆円、波及効果を含めると48.8兆円にも達するとされています。この経済効果は地域内の様々な産業に広がり、地域全体の経済循環を促進します。誰かが何かを購入すると、そのお金が別の誰かの所得につながるという経済の好循環が生まれます。
雇用の創出と観光関連産業の成長

観光振興は地域における雇用創出の重要な源泉となっています。観光関連産業は世界でも有数の雇用創出産業の一つであり、世界全体で1億1,800万人以上が直接雇用され、これは全雇用の3.8%に相当します。日本においても、観光に関連する雇用効果は393万人と推計されており、特に地方における雇用機会の創出に大きく貢献しています。
観光産業の雇用創出効果は、ホテルや旅館の従業員、ガイド、土産物店の販売員など多岐にわたります。また、観光産業の成長率は経済全体の成長率を上回るケースが多く、例えば2011年から2019年にかけて東南アジアの観光関連GDPは年6.7%の成長を記録しています。この成長性の高さは、観光産業が地域の持続的な発展と雇用創出に大きく寄与することを示しています。
税収増加と自治体への影響
観光振興は地方自治体の税収増加にも貢献します。観光客の増加に伴い、宿泊税や入湯税などの観光関連税収が増加するだけでなく、観光関連事業者の所得増加による法人税・住民税の増収、不動産価値の上昇による固定資産税の増収なども期待できます。
地価上昇による固定資産税収の増加は、自治体の9割で確認されており、これらの増収分は自治体の独自施策に活用できる自主財源となります。特に人口減少時代において、観光による交流人口の拡大は税収確保の重要な手段となっています。ただし、コロナ禍のような観光需要の急激な変動は税収にも影響を与えるため、安定した財政基盤の構築には多様な収入源の確保が必要です。
地域文化の再評価と保護
観光振興は地域の文化や伝統の再評価と保護にも大きく貢献します。観光客が地域の文化的資源に関心を持つことで、地域住民自身も自らの文化の価値を再認識する機会が生まれます。これにより、失われつつあった伝統文化や工芸技術の保存・継承への取り組みが活性化します。
地域の伝統文化を支える地域住民や民間企業との連携を図りながら、その一体的・総合的な保存及び活用を進めることで、地域の魅力を創出することができます。また、地域の歴史や文化を学ぶ教育カリキュラムの充実も、文化の継承と観光振興の両面で重要な役割を果たします。文化財の再評価は「ふるさと再発見」につながり、地域のアイデンティティ強化にも貢献します。
地域ブランドやデジタル化などの観光振興施策
効果的な観光振興には戦略的なアプローチが不可欠です。この章では、地域の魅力を最大化し、訪問者の満足度を高めるための具体的な施策について詳しく見ていきましょう。
地域特産品の開発と市場拡大
地域特産品の開発と市場拡大は、観光振興と地域経済活性化の重要な戦略です。地域特産品のブランド化は、単に認知度を高めるだけでなく、その地域ならではの品質、独自性、ストーリーを消費者に伝え、商品の付加価値を高める重要な手段となります。
効果的な地域特産品開発には、品質の統一と向上、地域の歴史や文化に根ざしたストーリー性の構築、魅力的なデザインとパッケージの開発が重要です。また、地域の特性を活かした商品開発、時代のニーズに合わせた新商品の開発、地元の生産者や企業とのコラボレーションなども成功の鍵となります。
販路拡大においては、地元市場でのプロモーションに加え、デジタルマーケティングを活用した国内外への展開も重要です。特に海外市場では日本の食文化や伝統工芸に対する関心が高まっており、輸出促進も地域特産品の発展に大きく寄与します。
観光イベントの効果的な企画と実施

観光イベントは地域の魅力を発信し、交流人口を拡大する効果的な手段です。成功する地域イベントの企画・運営には、地域資源を活かした独自性のある企画、効果的な情報発信、地域住民の参加促進などが重要です。
デジタルツールの活用も地域イベントの成功要因の一つです。例えば、令和5年に実施された造幣局の「桜の通り抜け」では事前予約制を導入するなど、デジタル技術を活用した運営改善が効果を上げています。また、他地域からの誘客を促進するためには、交通アクセスの整備や宿泊施設との連携も重要な要素となります。
地域イベントは一時的な集客だけでなく、リピーターの獲得や地域のブランディングにも貢献します。イベントを通じて地域の魅力を体験した観光客が再訪問したり、SNSなどで情報を拡散したりすることで、持続的な観光振興につながります。
観光DXには地域活性化クーポンがおすすめです。くわしい資料を今すぐダウンロード
伝統工芸と観光の連携
伝統工芸と観光の連携は、文化的価値の継承と経済的価値の創出を両立させる重要な取り組みです。日本各地に受け継がれてきた伝統工芸は、その地域独自の文化や技術を体現しており、観光資源として大きな可能性を秘めています。
佐賀県では、肥前びーどろと古唐津焼という2つの伝統工芸が、それぞれ異なるアプローチで観光化に成功しています。また、石川県と香川県では伝統工芸を楽しむスポットを連携して紹介するなど、広域的な取り組みも行われています。越前市観光協会は石川県小松市と富山県南砺市と連携し、外国人富裕層をターゲットにした広域連携を進めており、北陸新幹線の延伸を契機とした新たな観光戦略を展開しています。
伝統工芸の観光活用においては、伝統的な技法を守りながらも、現代のニーズに合わせた商品開発や体験プログラムの提供が重要です。伝統工芸の生産と自然資源利用の関係に着目し、文化多様性と観光の持続可能な関係を構築することも、今後の課題となっています。
観光マーケティングにおけるSNSの活用
SNSは観光マーケティングにおいて非常に効果的なツールとなっています。観光・旅行業界では景勝地などの写真や動画映えする被写体が多いこともあり、SNSを活用して成功した事例が増えています。
SNSマーケティングが観光業にもたらす主なメリットには、低コストで高い宣伝効果を得られること、視覚的に魅力を伝えやすいこと、口コミによる信頼性の向上、ターゲット層への効果的なアプローチが可能なことなどが挙げられます。特に比較的検討期間の長い観光業においては、SNSを活用して潜在顧客とのつながりを持ち、興味関心や好感度を高めていくことが、来訪者を増やすきっかけとなります。
インバウンド観光においても、SNSは重要な役割を果たしています。外国人観光客は旅行先の選定や情報収集にSNSを活用することが多く、多言語での情報発信や現地の生の声を伝えることで、訪日意欲を高める効果があります。
デジタル技術を活用した観光案内
観光DXは、デジタル技術を活用して既存の観光サービスの質を向上させたり、課題を解決したりすることを目的とした取り組みです。デジタルスタンプラリー、XR(AR、VR)、NFT連携などのデジタル技術を活用し、地域の文化財や資源を活かした観光誘客・地域活性化を図る取り組みが全国で広がっています。
日本商工会議所は観光DXの推進を担うデジタル人材育成の重要性を指摘しており、地方大学などでの高度観光人材育成プログラムの開発支援も提言しています。また、MaaSの推進による交通アクセスの改善も、観光DXの重要な要素となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により観光需要は大きく減少しましたが、デジタル技術を活用した安全安心な観光の確立に向けた取り組みも進められています。観光DXは単なる効率化だけでなく、新たな観光体験の創出や地域の魅力の再発見にもつながり、持続可能な観光地域づくりの基盤となっています。
観光DXには地域活性化クーポンがおすすめです。くわしい資料を今すぐダウンロード