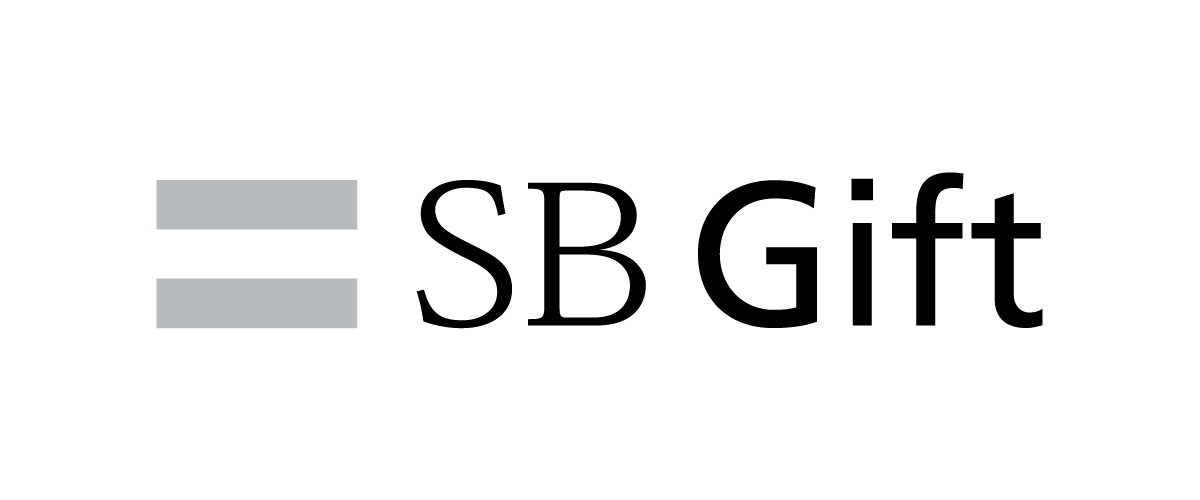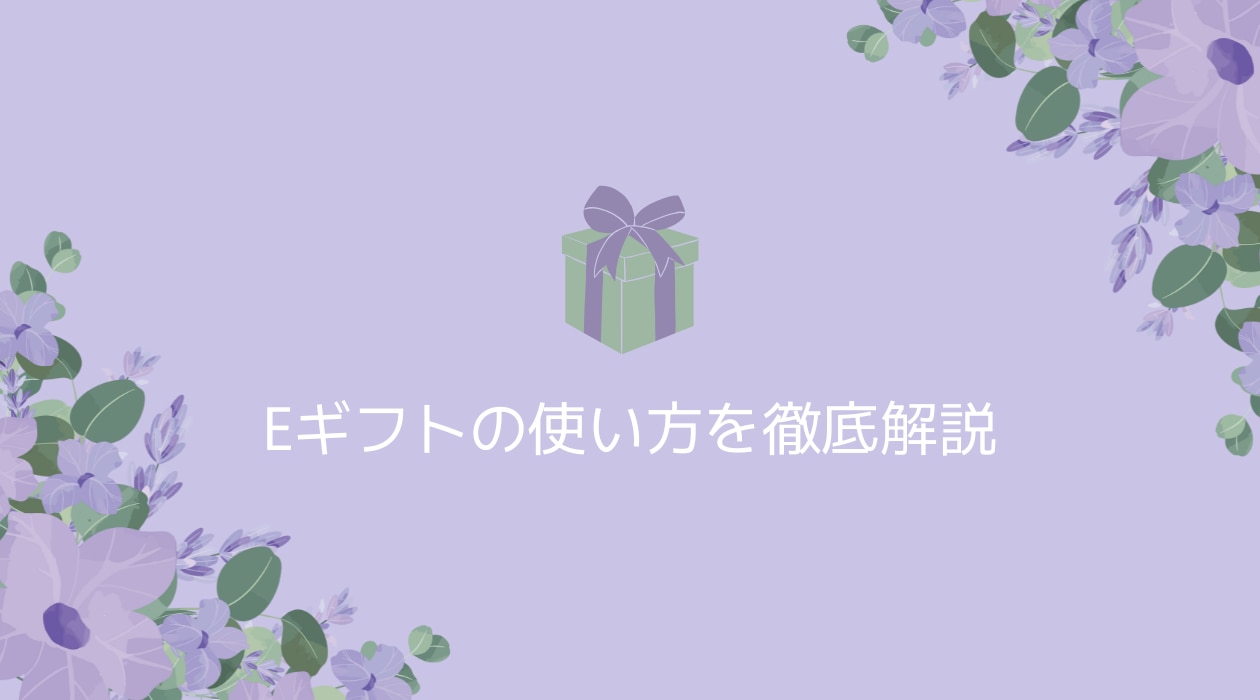
Eギフトの使い方を徹底解説 受け取り方から法人販促への活用事例まで
メールやSNSで手軽に贈れるEギフトは、個人利用だけでなく法人の販促キャンペーンでも活用が進んでいます。市場規模は2025年に4,057億円に達する見込みで、配送コストや在庫管理の手間を削減できる点が評価されています。本記事では、Eギフトの基本的な仕組みから受け取り方法、法人での活用事例までをわかりやすく解説します。
目次[非表示]
Eギフトとは?基本の仕組みと特徴
Eギフトの基本的な仕組みと種類について理解することで、自分の目的に合ったEギフトを選ぶことができます。
Eギフトの仕組みと種類を押さえよう
Eギフト(デジタルギフト)とは、商品や金券などをデジタル化し、URLやコードを通じてオンライン上で贈ることができるギフトサービスです。メールやSNS(LINE、X、Instagram、Facebook)を通じて送信でき、相手の住所を知らなくてもプレゼントを贈ることができます。
主なEギフトの種類は、コンビニやファストフード店などで商品と引き換えられる店舗受取型、各種ポイントや電子マネーとして利用できる金券型、受け取った側が商品を選べるカタログ型、そして配送先を指定して商品を受け取る配送型があります。サービス提供側がギフトURLを発行し、受け取り側がそのURLにアクセスして商品やクーポンを受け取る仕組みとなっています。
Eギフトのメリットを徹底解説
Eギフトには従来のギフトにはない様々なメリットがあり、個人利用から法人利用まで幅広く活用されています。
手軽で迅速に贈れる
Eギフトの最大のメリットは、その手軽さと迅速性です。従来のギフトでは商品の購入から発送、配達まで数日かかることが一般的でしたが、Eギフトであれば発行されたURLやコードをメールやSNSで送信するだけで、即座に相手に届けることができます。
また、実物の在庫を保管する必要がないため、在庫管理のコストやスペースも不要です。配送料もかからず、梱包や宛名書きの手間も発生しません。さらに、相手の住所や氏名といった個人情報を知る必要がないため、個人情報の管理リスクも軽減できます。
受け取る側にとっても、オンライン上でいつでもどこでも受け取ることができ、不在による再配達の心配もありません。自分の都合の良いタイミングで商品を引き換えたり、好きなものを選択したりできる利便性があります。
個人利用だけでなく法人利用にも最適
Eギフトは個人間の贈り物としてだけでなく、法人での活用が急速に進んでいます。調査によれば、販促キャンペーンやインセンティブで反応が良かったプレゼントとして、デジタルギフトが58.7%で第1位となっており、第2位の商品券・金券(47.7%)を11ポイント上回る結果となっています。
参照:https://cartaholdings.co.jp/news/20220224_1/
法人がEギフトを導入するメリットとして、低コストで大規模なキャンペーンを実施できる点が挙げられます。200円未満の少額から商品を選択できるため、予算に応じて柔軟に景品を用意できます。また、在庫リスクがないため、需要予測の難しさから解放され、必要な分だけ発行することが可能です。
さらに、デジタルギフトはオンライン完結のため、キャンペーンの効果測定も容易です。どの商品が選ばれたか、どの層に人気があるかなどのデータを分析することで、次回のキャンペーン改善につなげることができます。
法人向けEギフトの活用シーンとメリット

法人でのEギフト活用は、販促キャンペーンから従業員福利厚生まで、多岐にわたるシーンで効果を発揮しています。
販促キャンペーン(応募・抽選・全員プレゼント)
販促キャンペーンでのEギフト活用は、最も一般的な利用シーンです。SNSキャンペーンとの相性が特に良く、フォロー&リツイート、フォロー&いいねなどの応募条件を設定し、当選者にデジタルギフトを配布する形式が広く採用されています。
特にインスタントウィン形式のキャンペーンでは、その場で抽選結果がわかるため、ユーザーの参加モチベーションが高まりやすいという特徴があります。従来の物理的な景品では難しかった大規模キャンペーンも、Eギフトなら実施可能です。在庫管理や配送の手間がないため、全員プレゼントキャンペーンも低コストで実現できます。
アンケート回答の謝礼、資料請求のお礼、新規会員登録特典などにも活用されており、顧客接点の創出と顧客獲得を効率的に進めることができます。デジタルサンプリング施策として、商品引換券を配布し実際に体験してもらうプロモーションも効果的です。
顧客ロイヤルティ向上(お礼・誕生日特典など)
既存顧客との関係性を深めるために、Eギフトを活用する企業が増えています。顧客の誕生日や記念日に合わせてデジタルギフトを贈ることで、特別感を演出し、顧客満足度の向上につながります。
契約更新時や長期利用者への感謝の気持ちとして、定期的にギフトを贈る施策も効果的です。物理的なギフトと異なり、タイミングを逃さず即座に贈ることができるため、顧客体験の向上に寄与します。サービス利用促進のインセンティブとしても活用でき、アプリ利用や機能活用を促進することが可能です。
また、紹介プログラムの特典としてデジタルギフトを提供することで、既存顧客からの新規顧客紹介を促進し、口コミによる顧客獲得を実現できます。
従業員インセンティブ・福利厚生での導入
従業員向けのインセンティブや福利厚生としてのEギフト活用も広がっています。業績達成時の報奨金、社内表彰制度の副賞、永年勤続表彰のギフトとして利用されています。
誕生日ギフトとして活用する企業も多く、従来のAmazonギフトカードの郵送から、デジタルギフトに切り替えることで担当者の業務負担を大幅に削減できた事例があります。受け取る従業員側も、好きなタイミングで好きな商品を選べるため、満足度が高い傾向にあります。
繁忙期勤務の従業員への慰労ギフト、リモートワーク中の従業員へのコミュニケーション施策、オンライン周年祭のインセンティブなど、様々なシーンで活用されています。デジタルギフトを通じて企業と従業員の距離を縮め、エンゲージメントを高める効果が期待できます。
Eギフトの受け取り方と使い方ガイド
 Eギフトを受け取る際の基本的な手順と、利用時に注意すべきポイントを確認しておきましょう。
Eギフトを受け取る際の基本的な手順と、利用時に注意すべきポイントを確認しておきましょう。
受け取りステップ
Eギフトの一般的な受け取り方は、以下の3つのステップで完了します。まず、メールやSNSのダイレクトメッセージで送られてきたURLまたはバーコード、ギフトコードを受け取ります。スマートフォンやパソコンなど、インターネットに接続できる環境があれば受け取ることができます。
次に、受け取ったURLにアクセスし、ギフトの内容を確認します。選べるタイプのEギフトの場合は、複数の商品やサービスの中から自分が欲しいものを選択します。コンビニコーヒーやファストフード商品など、店舗で利用できるものや、各種ポイント、電子マネーなど、用途に応じて選ぶことができます。
最後に、店舗受取型の場合は、表示されたバーコードやQRコードを対象店舗のレジで提示し、商品と引き換えます。配送型の場合は、配送先住所を入力すると、指定した住所に商品が届きます。電子マネーやポイントの場合は、指定のアプリやサービスにチャージされます。
特別なアプリのダウンロードや会員登録は基本的に不要で、URLにアクセスするだけで利用できるサービスが多く、誰でも簡単に利用できる設計になっています。
有効期限や利用上の注意点
Eギフトを利用する際に最も注意すべき点は、有効期限です。多くのEギフトには受け取り期限やギフトコードの有効期限が設定されており、期限を過ぎると無効となり使用できなくなります。一般的に、有効期限は発行日から3ヶ月から6ヶ月程度ですが、サービスによって異なります。
受け取ったEギフトのURLやメールは削除せずに大切に保管し、有効期限を確認することが重要です。期限内に必ず手続きを完了させるよう、スケジュール管理をしておくことをおすすめします。有効期限の延長や再発行は基本的にできないため、注意が必要です。
また、Eギフトはオンライン上でのやり取りとなるため、インターネット接続環境が必要です。電波不良時やデバイス故障時には利用できないため、安定した通信環境で手続きを行いましょう。
店舗受取型のギフトの場合、対象店舗でのみ利用可能です。事前にどの店舗で利用できるか確認しておくことが大切です。電子マネーやポイント交換型の場合は、指定のアプリやサービスのアカウントが必要になる場合があります。
Eギフト導入のステップとポイント
法人でEギフトを導入する際の基本的な流れと、効果的な活用のためのポイントを押さえておきましょう。
導入までの流れ
法人がEギフトを導入する際の一般的な流れは、まずキャンペーンや施策の目的を明確にすることから始まります。新規顧客獲得、既存顧客満足度向上、従業員エンゲージメント向上など、目的によって最適なギフトの種類や配布方法が異なります。
次に、予算とターゲット層を考慮してギフトの種類を選定します。若年層向けであれば汎用性の高い電子マネーやポイント、幅広い年齢層向けであればコンビニやファストフードで使えるギフト、高単価のキャンペーンであればカタログギフトなど、目的に応じて選択します。
デジタルギフトサービスを提供する企業に問い合わせを行い、サービス内容、料金体系、初期費用、手数料、最小発注数などの詳細を確認します。多くのサービスでは、無料サンプルや体験版を提供しているため、実際に試してから導入を検討することができます。
契約後、ギフトの発注を行い、URLやギフトコードを受け取ります。配布方法はメール一斉送信、SNS配信、キャンペーンサイトでの自動発行など、様々な方法があります。配布後は、ギフトの利用状況や効果を測定し、次回のキャンペーン改善に活かすことが重要です。
SBギフトの法人向けEギフトサービス一覧
SBギフト株式会社は、2006年に設立されたデジタルギフト専門企業です。2008年から「ポチッとギフト」サービスを提供しており、15年以上の実績を持つパイオニア企業として、多くの法人企業から信頼を得ています。
SBギフトの強みは、豊富なサービスラインナップと長年の運用実績にあります。小規模なキャンペーンから大規模な販促施策まで、幅広いニーズに対応できる体制が整っており、キャンペーン設計から実施、効果測定までワンストップでサポートを受けることが可能です。